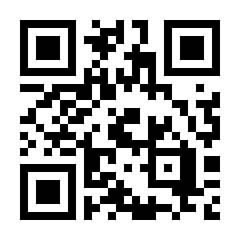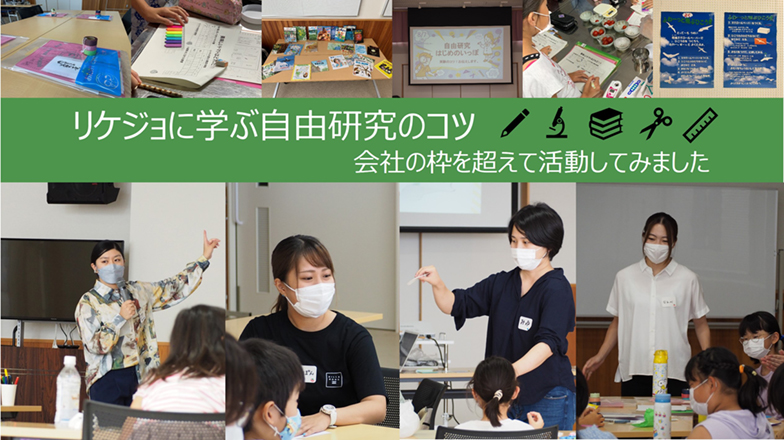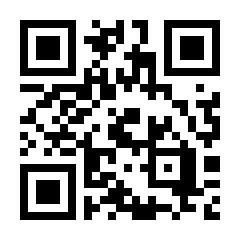(日本語) バナナの虜になったある男の話 ~ジヤトコOB・鈴木さんの第二の挑戦~
ある土曜日の朝6時半。筆者が運営しているインスタグラム@jatco_communityのDMに、「ジヤトコOBです」とのメッセージが届きました。なんと、前所属部署の大先輩、鈴木允さん!
お互いの近況をやり取りする中で、「今日、幼稚園にバナナを植えるんだけど、見に来ない?」とお誘いが。
行くに決まっています。
連絡をもらってから2時間後、富士市内のとある幼稚園で10年ぶりに允さんと再会しました。(在職中から親しみを込めて“允さん”と呼んでいたので、この記事でもそう呼ばせていただきます)

(日本語) バナナに取りつかれてしまった允さん
リタイア後は、趣味のウィンドサーフィンなどを楽しむ日々を送っていた允さん。しかし、地元・元吉原地区の少子化や地域の元気のなさが気になるようになったといいます。そんなとき耳にしたのが、露地でバナナを育てているという親戚の鈴木孝正さんの話。
当初「え、日本で露地バナナができるの?」と驚きつつも、面白そうだと感じた允さんは、件の孝正さんの畑に直行。すると、1年目にして166本ものバナナがなっていたではありませんか!
そこから允さんは正孝さんに合流。バナナ栽培のとりこに。なぜそこまで夢中になれるのか尋ねると、こんな答えが返ってきました。

(日本語) ボランティアメンバーの皆さんと一緒に汗を流して作業しています
「ジヤトコ時代、生産管理部(現SCM部)で納期に向けて仕事していた。その経験が今の栽培にも生きている。冬が来る前に収穫しなきゃいけないから、逆算して計画を立てて作業する。でも自然相手だから思い通りにいかない。トランスミッションを製造するより、よっぽど難しい。だから面白いんだよね。」
周囲からは「バナナなんて無理だろう」と否定的な声もありましたが、二人はあきらめず、周りに声をかけ続け、仲間とともに苗を増やしていきました。3年後には、当初通販で購入した1本の株が100株を超え、今では200株ほどに。“株分け待ち”の希望者が行列をつくるほど。
こうした活動の輪が広がり、東は神奈川西湘地区、西は静岡市、北は大渕地区まで広がりをみせています。昨年、「元吉原露地バナナの里の会」というコミュニティグループも結成され、允さんはその会長を務め、孝正さんは教授に就任。会員は60名を超えます。リタイアされた方々を中心に、果樹農家や元エンジニアなど、多彩なメンバーが集まり、富士市に“バナナ文化”を広めようと、非営利・ボランティアで活動を続けています。
この活動の根底には、SDGsへの貢献や地球温暖化、子供たちへの情操教育など、社会的な視点も含まれており、更には熱帯植物の内需拡大という新たな挑戦にもつながっています。
「バナナを通じて、人と人のつながりが“点”から“線”へ、そして“面”へと広がっていく。それが何よりの喜びだよ。」
と語る允さんの目は、本当に生き生きとしていました。
(日本語) 広がるバナナの輪――地域へ、そして未来へ
幼稚園の畑で出会った、もう一人の“バナナの会”メンバー、大嶽さん。
彼女はこう話してくれました。
「会長さんの投稿をSNSで見て、“富士でバナナ!?”って驚きました。面白そうだなと思っていたら、共通の知人がいて…気がづけば“バナナの会”に入っていました。」
今では自発的に広報的な役割を担い、活動の魅力を写真や文章で記録。3月には第1回“バナナの株主総会”を開催し、バナナの歴史や育成スケジュールを共有する場も生まれました。
「SNSがつないだご縁が、またここにもあるんですよね。」

(日本語) 作業を見守る大嶽さん
“バナナの会”のメンバーたちは、ただ苗を植えるだけではありません。地域の幼稚園や小学校にバナナを植え、子どもたちと育てる取り組みもスタート。そして、高齢者施設やお寺など、“人が集う場所”にもバナナを届ける活動も始まっています。
また、允さんは農業高校の先生や大学にも問い合わせを行い、バナナの病気や土質に関する情報収集や、育成方法共有も欠かしません。日本では輸入率98%のバナナ。専門家が少ない中、鈴木さんのもとに相談が寄せられることもあるのだとか。
そんな真摯な姿勢は、現役時代にも通じるものがあります。
「納期を守るために、計画を立て、実行していく。今は自然と向き合い、人とつながりながら新たな挑戦をしている。いまのほうが、ずっと“允さんらしく”輝いているように見えます。」
「元吉原露地バナナの里の会」の皆さんが育てているのは、零下5度まで耐寒性のあるブルージャバ種(通称アイスクリームバナナ)と、もうひとつはドワーフ・ナムワ。
年間を通して気候が温暖で安定している富士市だからこそ、この“ロジバナナ”は育つのだそうです。
「Bell Banana」という名前は、鈴木さんの「鈴(Bell)」にちなんで命名されたもの。あっさりとした上品な味わいが特徴で、11月~12月には2000本の収穫が期待できるそう。今から待ち遠しいです。

SNSから始まった小さな出会いが、地域を元気にし、未来へつながっていく。
@jatco_community を運営していて、人とひとがつながることの喜びを、これほど間近に感じた出来事はありませんでした。
これからも、そんな温かいご縁を大切に紡いでいきたいと思います。