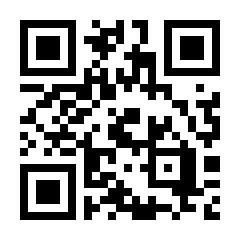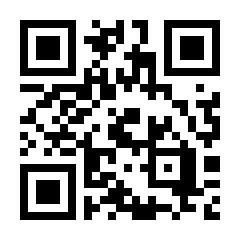ジヤトコは7年連続で「健康経営優良法人(ホワイト500)」に認定されています。 食育イベントや社内ジムの開設など、健康づくりの取り組みは従業員の皆さんにも身近な存在となりました。一方で、「安全」に関しては、どのような活動が行われているのでしょうか。 今回は、安全健康管理部の小笠原部長と秋山課長に、安全の基本的な考え方や日々の取り組みについて伺いました。
「安全」とは、当たり前に守られるもの
小笠原さん: 私たちは“ものづくり”の会社です。生産設備が多く、常に危険と隣り合わせの現場で働いています。従業員がケガをしない・させない環境を整えることが、私たち安全健康管理部の使命です。
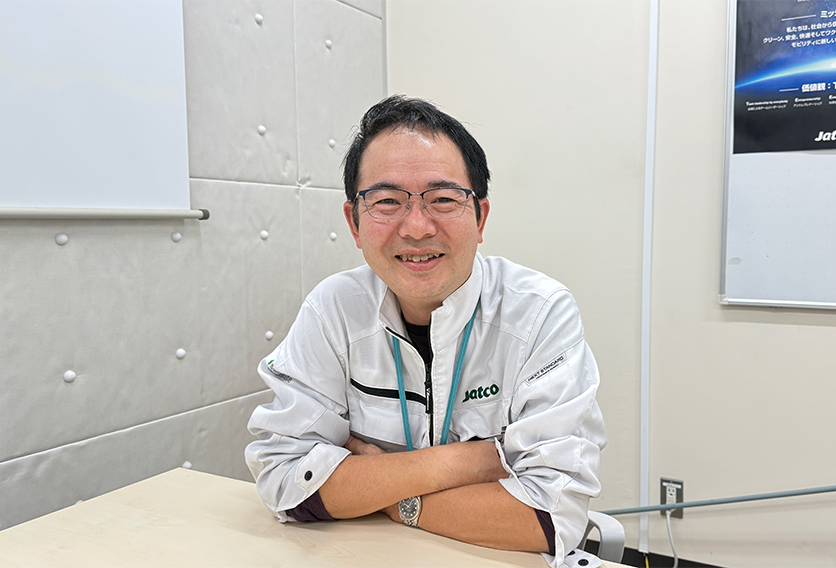
安全健康管理部部長 小笠原さん
いつも朗らかな笑顔ですが、安全について語るときは仕事人の顔でした
秋山さん: 安全とは、従業員が“当たり前に享受できるもの”だと思います。毎日元気に出社し、ケガなく健康な状態で帰宅できること――その“当たり前”が保証されている状態が、安全なのです。

安全健康管理部課長 秋山さん
安全は“当たり前”に守られるものという信念のもと仕事に励んでいます
安全活動の3つの柱
ジヤトコの全社安全方針は、次の3つの柱で構成されています。
① 安全な人づくり(安全マインド教育)
体感訓練道場では、不安全行動がどれほど危険なのかを実際に体験できます。 また、入社時の安全教育や毎月の交通KY(危険予知)活動、7月の全国安全週間での啓発活動、安全標語の募集など、従業員一人ひとりが安全について考える機会を設けています。 「安全は知識ではなく心に根づくもの。だからこそ“心に訴える安全教育”を繰り返し行っています。」

安全宣言式の様子
② 安全な設備・作業方法の実現
リスクアセスメントによって職場に潜む危険を洗い出し、優先順位をつけて対応しています。 これまで行ってきたヒヤリハット活動をさらに強化し、「気がかりヒヤリハット活動」と称して、ヒヤリハットまではいかないかもしれないが、もしかしたら危険が潜んでいるかもしれないという、気にする範囲を拡大して危険の芽を事前に摘みとる仕組みも構築しました。 「上長が安全を把握して対応することはもちろん大切ですが、現場を一番よく知っているのは実際に現場で働く人たちです。従業員自身が主体的に危険を見つけ、改善できる文化を育てています。」
③ 同じ災害を二度と起こさない
過去に実際にジヤトコで発生した災害を定期的にリマインドし、再発防止に努めています。 モザイクはかけていますが、実際の災害現場や怪我の画像を見せることで自分事化して欲しいと思っています。 「安全は一度築いて終わりではありません。人は忘れる生き物。だからこそ、繰り返し思い出すことが大切なのです。」
この3つの柱は、それぞれが独立しているようでいて、実はすべてがつながっています。 「安全な人」が「安全な設備・作業」を支え、「過去の教訓」を忘れずに活かすことで、ジヤトコらしい安全文化が形づくられます。そして、安全は特別な活動ではなく、日々の仕事の中で積み重ねられる“当たり前の行動”によって守られていくものです。
現場とともに支える安全のリーダーたち
製造部門では、各課に「安全健康係長」が配置されています。 安全が最重要テーマであるため、現場経験の豊富な人財が任命され、日々の安全活動をリードしています。現場を知っているからこそ、細かな危険にも目配りができるのです。近年では、次世代リーダー育成の一環として、安全健康係長の経験を積ませる動きも広がっています。 「安全健康係長の人選には役員も関わっています。それほどまでに“安全”は会社の根幹なのです。」
悲しむ人を出さないために
安全活動の根底にあるのは、「従業員一人ひとりの人生を守る」という思いです。
小笠原さん: 私たちの仕事は、家族や仲間、友人など“あなたのケガを悲しむ人”を出さないことです。安全は一人では守れません。従業員の皆さんの理解と協力があってこそ成り立ちます。
秋山さん: 安全健康管理部は、行政・司法・立法のすべての機能を持つ部署です。ときには厳しいことを言わなければならない場面もありますが、現場に寄り添い、一緒に解決策を見つけていくことを大切にしています。現場から“ありがとう”と言ってもらえた瞬間が、いちばんのやりがいです。
小笠原さん: “安全絶対”は基本中の基本。人は慣れる生き物ですが、安全は決して慣れてはいけません。 日々の啓発活動を通して、短い時間でもいいので“自分にとっての安全”を考える時間を持ってもらいたいと思います。
日々の「当たり前」を守るために
安全維持は製造現場だけの課題ではありません。階段の昇り降りで手すりを使わない、段差につまずく、事務用品で手を切る、ながらスマホ、ポケットに手を入れて歩く――といった身近にも危険が潜んでいます。運動能力の低下はケガにもつながりますので、健康づくりそのものが安全の土台なのです。 私たちは経済活動の中で、ついコストや効率を優先しがちですが、災害が起こると生産を止めざるおを得ないリスクがあります。だからこそ、日々の“当たり前の安全”がしっかりと確保されているからこそ、安心して仕事に取り組むことができるのです。 “当たり前の安全”を維持するためには、従業員一人ひとりの協力が大切です。「皆が無事に一日を終える」――その積み重ねが、会社の未来を支えています。
リニューアルした安全道場
安全健康係長のひとり、平野さんに、今年度リニューアルした安全道場を案内してもらいました。 安全道場は、実際に危険を“体感する”ことで恐怖を知り、「なぜ起きてしまったのか」を考えることを目的としています。 場内には10以上の危険体感設備があり、説明員として立つことができるのは、教育を受けた10名のトレーナーのみ。 正しく“怖がらせる”、そして“考えさせる”ためには、教える側の水準も問われます。 実際に体験してみると、思わず慌ててしまい、「この行動は危ない」と身をもって実感しました。 台車や脚立など、製造現場以外の人でも扱う道具に危険が潜んでいることを知り、「自分事」として捉えることができました。

リニューアルされた安全道場

指差し呼称体感機

切粉の鋭さを体感

油まみれの床面を歩く体験
現場を想う、目に見えない努力
安全健康管理部の目に見えない努力が、今日もジヤトコの“当たり前”を支えています。 インタビュー中も、小笠原さんと秋山さんの携帯はひっきりなしに鳴っていました。それでも二人は落ち着いて一つひとつ対応し、気配りを忘れません。その姿からは、数字や制度では表せない従業員を想う気持ちがしっかりと伝わってきました。 私たちも日々の生活の中で安全を意識し、毎日元気に「ただいま」と言えるように心がけていきましょう。

従業員の安全と健康を守る専門チーム 安康担当・産業医・保健師は、「信頼・清潔・安全」を象徴する白いユニフォームを着用し、日々職場の健康と安全を支えています。